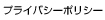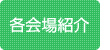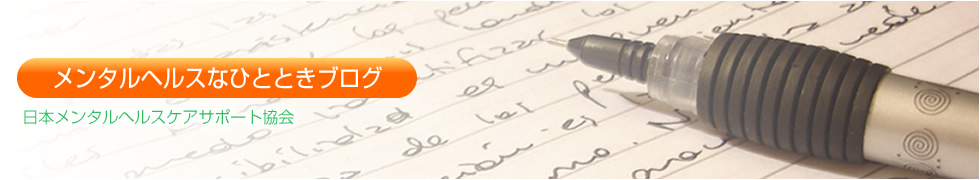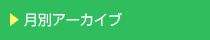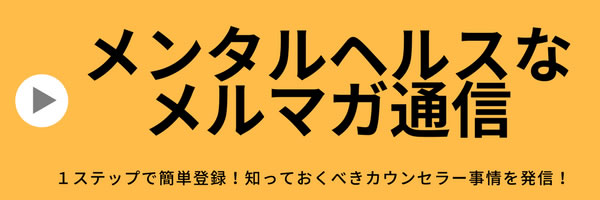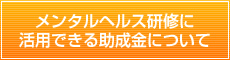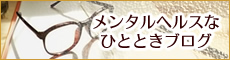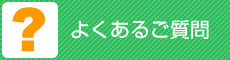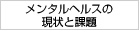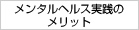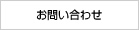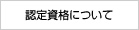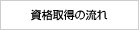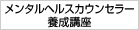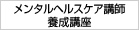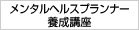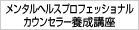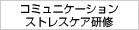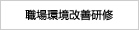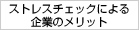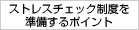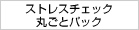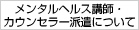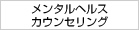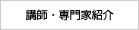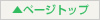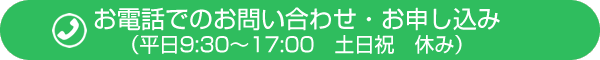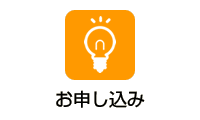2013年7月アーカイブ
メンタルヘルス不調の兆候はまず身体から (13/07/14)
メンタルヘルス不調は身体のサインをまず見逃さないことが大切です。
メンタルヘルス不調の兆候は、体がだるくて疲れがとれない、息苦しいなど、眠れない、頭痛、めまいなど身体面の症状が先に出ます。
この段階では医者へ行っても原因がつかみづらいことが多く、軽視しがちです。
ここでストレスが原因かも?と少し疑ってゆっくり休む時間をとる、食事を3度とるなど、身体のバランスを
整える時間を作ってください。
それがメンタルヘルス不調を防止する大きな対策になります。
・サインに気づき、メンタルヘルスセルフケアを行う方法が身につくストレスケア研修は、こちら。
メンタルヘルス不調は身近な症状 (13/07/13)
メンタルヘルス不調は「心の風邪」と言われるくらい、ある日突然、誰にでもやってくる病気です。
メンタルヘルス不調はかかる前に前兆はあります。
*身体の風邪の前兆・・・悪寒・寒気・熱っぽい・くしゃみ等
*心の風邪の前兆・・・意欲低下・食欲不振・頭痛・便秘・下痢等
しっかりとメンタルヘルス不調の前兆をしって、心の風邪対策をしましょう。
・メンタルヘルスの全般の技術が習得できるメンタルヘルスカウンセラー養成講座はこちら。
メンタルヘルスケア検定とは (13/07/11)
皆様こんにちは!代表 奥江 裕理です。
メンタルヘルスケア検定は職場で起こるストレスやメンタルヘルスに関わる一般的知識と会話能力を判定する検定です。
メンタルヘルス不全による実際起こり得ることの対処法や早期発見ポイントも知ることができる検定です。
メンタルヘルスケア検定に合格することにより、部下のうつ病による休職といったリスク回避だけでなく、相談時の応対法が分かります。
また職場で起こるご自身のストレスケア、メンタルヘルス不全予兆に気づくことができ、仕事への悪影響を回避する効果があります。
締め切りは9月25日です。
この機会にぜひメンタルヘルスケアを習得し、ご自身のために、お近くの方のケアにお役立てください。。
*メンタルヘルス検定はこちら
*NPO法人日本メンタルヘルスケアサポート協会
IT関連業界とメンタルヘルス対策 (13/07/10)
IT関連業界は特にメンタルヘルス不調者が多い業種です。
メンタルヘルス不調者が多い理由として、パソコンの前に座り、誰とも話をしない。
連絡は全てパソコンで、コミュニケーションとる機会がない。
一日中座っていることも多く、パソコンと同じ道具に思えてくる。 等です。
対策として、①定期的に面談を実施し、日頃の働き方や心の状況を確認する。
②ストレスチェックなども実施。
③日常のコミュニケーションがメンタル不全を起こさないための最善策。
IT業界の方は自分がメンタルヘルス不全にならないためにも、会社でどんなメンタルヘルス対策を行っているのか確認してみるのもよいでしょう。
・メンタルヘルス対策に必要な知識が得られるメンタルヘルスケア研修はこちら。
当協会がNPO法人になりました。 (13/07/09)
皆様こんにちは!代表 奥江 裕理です。
6月28日付けで『日本メンタルヘルスケアサポート協会』は『NPO法人 日本メンタルヘルスケアサポート協会』として活動いたします。
今後とも皆様の変わらぬご支援、御愛顧の程、何卒よろしくお願いいたします。
メンタルヘルスカウンセラー養成講座とは (13/07/08)
NPO法人日本メンタルヘルスケアサポート協会ではメンタルヘルスカウンセラー養成講座を行っております。
この講座はメンタルヘルスの知識、関わり方、傾聴法を習得するための講座です。社内のメンタルヘルス担当者、また協会のカウンセラー、講師も養成します。
日本メンタルヘルスケアサポート協会のメンタルヘルスカウンセラー構成講座には下に挙げるような種類があります。
・メンタルヘルスカウンセラー初級
・プロフェッショナルカウンセラー
・キャリアインストラクター
・エグゼクティブインストラクター
それぞれの資格を取得すると「合格認定書」が発行されるとともに、インストラクターの資格を取得すると日本メンタルヘルスケアサポート協会公認の講師として登録することが可能です。
社内のメンタルヘルス担当者として指導できると同時に、日本メンタルヘルスケアサポート協会が主催する様々な講座の講師として活躍することができます。
・メンタルヘルスカウンセラー養成講座については、こちら。
傾聴力は日常で身に付ける (13/07/04)
傾聴力について、色々な書籍、研修があります。
ただ自分のものにするため大切なのは使うこと。
なぜかというと、スキルだからです。スキルは学んでも行動としてトレーニングをないと身につきません。
実際に、日本メンタルヘルスケアサポート協会の傾聴トレーニング研修を学ばれる多くの方が、
「聴くって難しいのですね。」と言われます。
普段の生活の中で常に「聴く」を意識しているだけで自然と身に付くものです。
スキルを学んだら、発言の前に傾聴を心かけてみてください。
傾聴トレーニングについてはこちら。